
おはようございます!(業界人気取り)
今日も相場があれていましたね。SBIのアプリの通知でも株価荒れ注意報きてたし。
今日は前回にの優待株投資のメリットに対応する、優待株投資のデメリットについてまとめていこうと思います。
メリット、デメリットを踏まえたうえで、ぜひご自身で選択を!

株価の変動リスク
・優待目当てで買った株が値下がりし、権利確定日後に大きく下落し結果的に損をする可能性がある。
前回のメリットのところでも紹介した、「権利落ち」の話ですね。せっかく投資したのに収支がマイナスになったら、

貯金だけやったらお金が増えへん。インフレ率考えたら逆に目減りするだけやって聞いて、株買ったのに逆に下がってもうてるやん。。。
最悪や、早めに売ったほうがええかな?でも、上がるかも。優待ももらってるし。。
どうすればええんやー!
と、なってしまいますね。総資産を増やすために始めたのに減っては意味がない。となってしまうリスクがあります。

引き続きTradingView様からお借りしました。
ヴィレッジバンガードの株価の流れなんですが。赤丸のところで下がっていますね。所有している株の価値がさがったらテンションが下がってしまうのは人のサガなのでしょうか。
・優待廃止や改悪が発表されると、株価が大きく下落することがある。
これは、優待株投資にはさけられない、分散しながら事故?だと思うしかないのでしょうか。
優待の価値が個人のニーズに左右される
・優待内容が自分にとって使いにくいものだと、実質的なメリットが少ない。
これは普段自分が使わない業種だと使い道がなく。せっかくの優待を生かせず、損をしてしまうということです。たとえば、結婚する気がないのに結婚の挙式代金の割引券をもらったり。自分の住んでいる地域にまったくない飲食店の金券をもらっても意味がないですよね。
・優待内容は魅力的でも、配当利回りが低い場合がある。
優待株は配当金が少なめに設定されていることが多いので、優待を使うことができなければ、余計に損をしてしまっているということにもなってしまいます。
長期保有の縛りが増えている
・最近は「1年以上保有しないと優待がもらえない」といった条件を設ける企業が増加。
「1年以上保有」が条件だったり、「1年以上保有でクオカードに〇円追加」のように、ながいこと保有してもらうために企業が条件を付けていることがあります。買ってすぐもらえないのは、なかなかじれったく、人気が下がってしまう原因にもなりえます。
・短期間での売買がしにくく、機動的な資産運用に向かない場合がある。
なので、「株価が下がる前に売ろう!」とか、「一度売っておいて、株価が上り始める権利確定日の5か月前に買おう!にやにや」などという、流動的な投資がしづらいこともデメリットとしてあげられます。
管理の手間がかかる
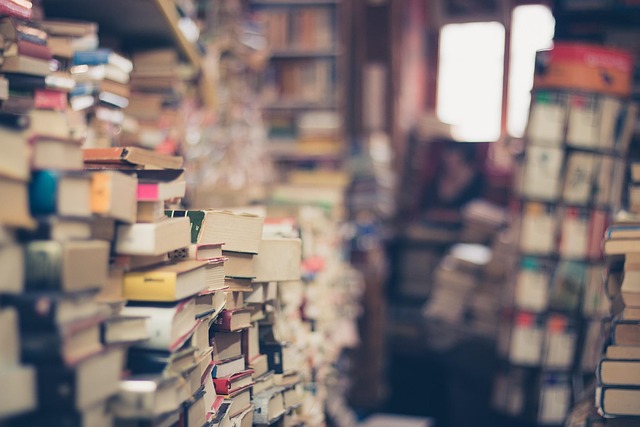
・複数の優待銘柄を保有すると、優待の管理や申請が煩雑になる。
・住所変更や引っ越し時に、優待品が届かなくなるリスクもある。
優待株も、カタログギフトからどの優待が良いか選んだり、株主番号を入力してアプリを通してポイントを付与されたりと、株によって形式が色々とちがうので、すべて把握し、整理する必要があります。また、使用期限等もあるので、きちんと管理をしておかないと金券が紙切れになってしまうことも。トホホですね。

期限には気をつけんとあかんな。。。
最後に
以上のデメリットを踏まえて、優待株投資にチャレンジしてほしいです。
とはいえ、わたしもまだまだ勉強中なので、リスク管理をしながら理想の形を探していこうと思います。
ぜひぜひおすすめの投資法、優待株があればコメント欄に書き込みをお願いします。

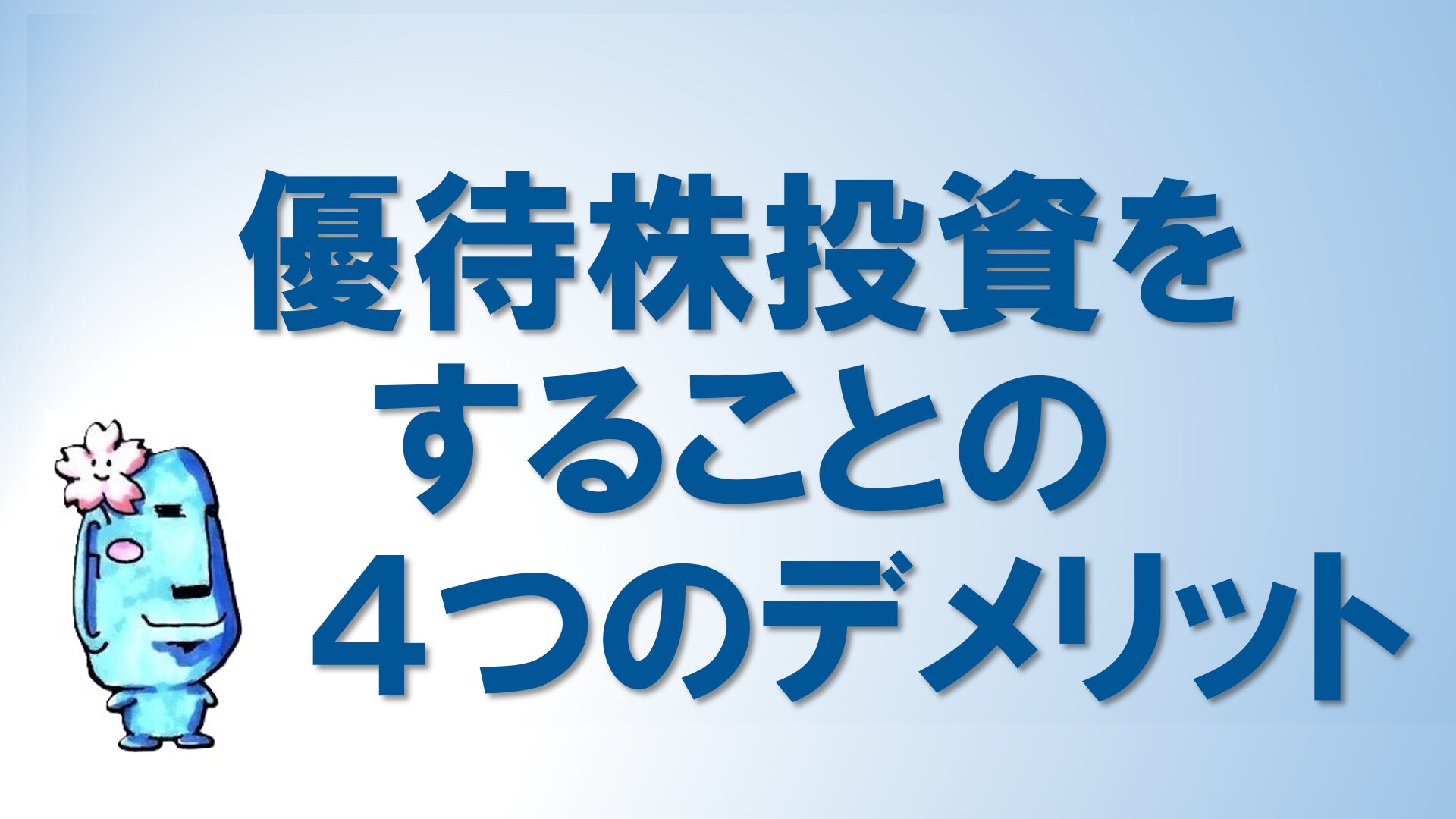


コメント